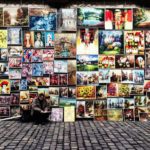多くの日本のEC事業者では、SEO専任チームどころか、マーケティング担当者や商品担当者、時には経営者自身が他の業務と兼任でSEOに取り組んでいるのが現実です。そして、正しい知識を学び、限られた時間の中で懸命に対策を実施しているにもかかわらず、検索順位は安定せず、オーガニックトラフィックは伸び悩み、売上への貢献も見えにくい。その結果、「うちにはSEOのプロがいないから仕方ない」「もっと勉強すべきなのか」と自責の念に駆られる担当者も少なくありません。しかし、本当の問題は担当者の能力や努力不足ではなく、会社の仕組みそのものにあることがほとんどです。
SEOを「誰かの片手間業務」にしている時点で失敗は決まっている
日本の多くのEC事業者では、SEOは「ついでにやる仕事」として扱われています。商品登録のついでにタイトルを考え、ブログ更新のついでにキーワードを入れ、サイトリニューアルのついでにSEO対策も、という具合です。しかし、現代のSEO、特にAI時代のSEOは、そんな片手間で対応できるほど単純ではありません。
例えば、新商品の発売時。商品企画部門は魅力的な商品を開発し、仕入れ部門は在庫を確保し、ECサイト担当者は急いで商品ページを作成します。しかし、その商品がどんなキーワードで検索されるのか、競合他社はどんな訴求をしているのか、商品説明文はAIに理解されやすい構造になっているのか、こうした検討は後回しになりがちです。結果として、素晴らしい商品なのに検索結果に表示されない、という事態が発生します。
EC事業者がSEOで失敗する5つの構造的理由
1. 検索からの集客を「経営課題」として認識していない
多くの中小EC事業者では、「SEOは大事」と言いながら、実際には広告費を削減するための代替手段程度にしか考えていません。経営者が本気で検索からの集客を重視していれば、専任者を置くか、少なくとも明確な責任者と権限を定めるはずです。
実際によくあるケースとして、ECサイトのリニューアルが決まった時、デザインや機能については何度も会議を重ねるのに、SEOへの影響については誰も考えていない、ということがあります。リニューアル後に検索順位が大幅に下落し、慌ててSEO会社に相談する、という悪循環を繰り返している企業も少なくありません。
2. 短期的な売上目標とSEOの時間軸のミスマッチ
EC事業者の多くは月次、四半期の売上目標に追われています。今月の売上が足りなければ広告を増やし、セールを実施し、メルマガを送ります。一方、SEOの効果が現れるまでには最低でも3〜6ヶ月かかることが一般的です。この時間軸のミスマッチにより、SEO施策は常に優先順位が下げられ、「時間がある時にやる」仕事になってしまいます。
また、担当者の評価も短期的な成果で行われることが多く、コツコツと構造化データを整備したり、コンテンツの品質を改善したりといった地道な作業は評価されにくいのが現実です。
3. 量産型コンテンツ戦略の罠
「コンテンツマーケティングが大事」と聞いて、とにかく商品説明やブログ記事を量産する企業があります。しかし、AIが検索結果を生成する時代において、単なる情報の羅列は価値を持ちません。ユーザーの疑問に的確に答え、商品の使用シーンを具体的にイメージさせ、購買の不安を解消する、そんな「本当に役立つ」コンテンツでなければ、検索エンジンにもAIにも評価されません。
例えば、化粧品を販売するECサイトが「○○成分配合」「○○エキス配合」といった成分の羅列だけで商品ページを作っても、「30代の乾燥肌に効果があるのか」「敏感肌でも使えるのか」といったユーザーの本当の疑問には答えていません。
4. システムの制約と部門間の壁
多くのEC事業者が使用しているASPカートやパッケージ型のECシステムは、SEOの観点から見ると制約が多いのが現実です。ページタイトルの自由な設定ができない、構造化データが実装できない、表示速度が遅い、といった技術的な問題を抱えながら、システムの変更には莫大なコストがかかるため、現状維持を選択せざるを得ません。
さらに、商品企画、仕入れ、EC運営、マーケティングといった部門がそれぞれ独立して動いており、SEOの観点から見た最適化は誰の仕事でもない、という状況が生まれています。
5. SEOを体系的に管理する仕組みの不在
大企業のようなSEOチームがない以上、より重要なのは「仕組み」です。新商品登録時のSEOチェックリスト、コンテンツ作成時のキーワード選定プロセス、定期的な順位モニタリングと改善サイクル、こうした仕組みがないまま、担当者の記憶と経験だけに頼っていては、継続的な改善は望めません。
また、担当者が退職した途端にSEOの知見が失われ、振り出しに戻るという事態も頻繁に発生します。
個人の努力ではなく、会社の仕組みを変える
SEO担当者(兼任であっても)は、現状でできることを精一杯やっています。問題は、その努力が実を結ぶための土壌が会社に整っていないことです。経営者がこれを個人の問題ではなく組織の問題として認識すれば、改善への道が開けます。
経営者が自問すべき5つの質問
「なぜうちのSEOはうまくいかないのか」と担当者を責める前に、以下を自問してください。検索からの集客を本当に重要だと考えているか、それとも「できればいいな」程度か。SEOの成果が出るまでの時間を理解し、それに見合った評価制度を作っているか。顧客にとって本当に価値のあるコンテンツを作る体制があるか。SEOに必要な技術的改善を実施できる体制があるか。SEOの知識や成果を組織として蓄積・継承する仕組みがあるか。
まとめ:小さな一歩から始める組織改革
専任のSEOチームを作ることが難しい中小EC事業者こそ、SEOを「誰かの仕事」ではなく「みんなの仕事」として捉え直す必要があります。商品企画の段階でキーワードニーズを調査する、新商品登録時にSEOチェックリストを使う、月1回は検索順位と流入キーワードを確認する、こうした小さな仕組みづくりから始めることで、個人の努力が成果につながる環境を作ることができます。
SEOの失敗は、担当者の能力不足ではありません。会社がSEOを成功させる仕組みを持っていないことが真の原因です。この認識を持つことが、EC事業のSEO改革の第一歩となるでしょう。
引用: searchengineland

齋藤 竹紘(さいとう・たけひろ)
株式会社オルセル 代表取締役 / 「うるチカラ」編集長
Experience|実務経験
2007年の株式会社オルセル創業から 17 年間で、EC・Web 領域の課題解決を
4,500 社以上 に提供。立ち上げから日本トップクラスのEC事業の売上向上に携わり、
“売る力” を磨いてきた現場型コンサルタント。
Expertise|専門性
技術評論社刊『今すぐ使えるかんたん Shopify ネットショップ作成入門』(共著、2022 年)ほか、
AI × EC の実践知を解説する書籍・講演多数。gihyo.jp
Authoritativeness|権威性
自社運営メディア
「うるチカラ」で AI 活用や EC 成長戦略を発信し、業界の最前線をリード。
運営会社は EC 総合ソリューション企業株式会社オルセル。
Trustworthiness|信頼性
東京都千代田区飯田橋本社。公式サイト alsel.co.jp および uruchikara.jp にて
実績・事例を公開。お問い合わせは
info@alsel.co.jp まで。